信用取引の要、委託保証金とは?担保の基本を解説

投資の初心者
委託保証金について教えてください。信用取引で担保として預けるお金のことですよね?現金以外に株も担保にできると聞きましたが、どういうことでしょうか?

投資アドバイザー
はい、その通りです。委託保証金は信用取引をする際に証券会社に預ける担保のことです。現金だけでなく、おっしゃる通り株などの有価証券も担保として利用できます。株を担保にする場合は、その時の市場価格に一定の割合をかけた金額が担保としての評価額になります。

投資の初心者
市場価格に一定の割合をかけるというのは、どうしてですか?例えば、100万円の株を持っていたら、そのまま100万円分の担保になるわけではないということですか?

投資アドバイザー
良い質問ですね。株価は常に変動しますので、担保としての価値も変動します。もし株価が大きく下落した場合、担保としての価値も下がってしまいますよね。そのため、株価に一定の割合(例えば80%など)をかけて、株価下落のリスクを考慮した上で担保評価額を算出するのです。100万円の株でも、80%なら80万円として評価されることになります。
委託保証金とは。
信用取引という、証券会社からお金や株券を借りて行う売買において、担保として証券会社に預ける現金や有価証券を『委託保証金』と言います。現金を預ける場合はその金額がそのまま担保としての価値になりますが、株などの有価証券を預ける場合は、その時の価格に一定の割合を掛けた金額が担保としての価値になります。
委託保証金の定義と役割

信用取引を行う際に証券会社に預ける担保が委託保証金です。これは、現金の他に有価証券も含まれます。信用取引では、自己資金を超える取引が可能なため、大きな利益を得る可能性がありますが、同時に損失も拡大する危険性があります。委託保証金は、証券会社がこの危険を管理するための仕組みであり、投資家にとっては自己資金を守るための安全装置としての役割を果たします。もし株価が予想と反対に動いた場合、損失は委託保証金から補填され、投資家の損失が一定の範囲を超えるのを防ぎます。委託保証金は、信用取引を行うための必要条件であり、その仕組みを理解することは、危険を適切に管理し、安全な投資を行う上で非常に重要です。投資家は、自身の投資目標や危険許容度に合わせて、適切な委託保証金の額を設定することが大切です。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 委託保証金 | 信用取引を行う際に証券会社に預ける担保(現金または有価証券) |
| 役割 |
|
| 重要性 |
|
現金と有価証券の評価額
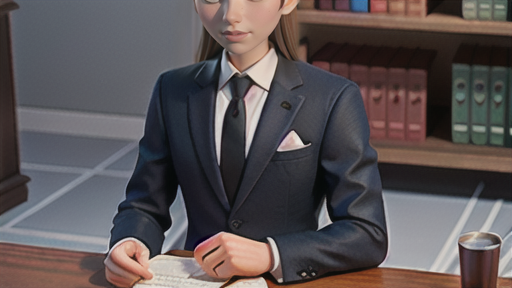
委託保証金として活用できる資産には、現金と有価証券があります。現金の評価額は、その額面金額がそのまま適用されます。一方、有価証券の場合は、市場価格に一定の割合を乗じた金額が評価額となります。この割合は、証券会社や有価証券の種類によって異なり、株価変動のリスクなどを考慮して、市場価格よりも低い水準に設定されるのが一般的です。例えば、株式の市場価格が1,000円で、乗じる割合が80%の場合、委託保証金としての評価額は800円となります。有価証券の評価額は市場の状況や個別の銘柄のリスクに応じて変動するため、常に最新の情報を確認することが大切です。また、証券会社によっては、特定の銘柄を担保として認めない場合もありますので、事前に確認が必要です。さらに、有価証券の評価額は日々変動するため、委託保証金の維持率にも影響を与えます。株価が下落すれば評価額も下がり、維持率が低下する可能性があるため、市場の動向を常に監視し、必要に応じて追加の保証金を預け入れるなどの対策を講じましょう。
| 資産の種類 | 評価額の算出方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 現金 | 額面金額 | |
| 有価証券 | 市場価格 × 一定の割合 |
|
委託保証金維持率とは

委託保証金維持率とは、信用取引を行う上で、投資家が必ず意識すべき重要な指標です。これは、証券会社に預けている保証金が、信用取引で建てたポジションに対してどの程度の割合を占めているかを示すものです。この割合が一定水準を下回ると、追加で保証金を預ける必要が生じます。これが一般的に「追証」と呼ばれるものです。追証が発生すると、指定された期日までに対応しなければ、証券会社によって強制的にポジションが決済されてしまうことがあります。株価が予想と反対方向に動いた場合や、取引量を増やしすぎた場合に、委託保証金維持率は低下します。そのため、信用取引を行う際は、常にこの維持率を把握し、リスク管理を徹底することが不可欠です。十分な保証金を預けておくことや、無理のない取引計画を立てることが、安全な信用取引につながります。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 委託保証金維持率 | 証券会社に預けている保証金が、信用取引で建てたポジションに対してどの程度の割合を占めているかを示す指標 |
| 追証 | 委託保証金維持率が一定水準を下回った場合に、追加で保証金を預ける必要が生じること |
| 強制決済 | 追証が発生し、指定された期日までに対応しない場合、証券会社によってポジションが強制的に決済されること |
| 維持率低下の要因 | 株価が予想と反対方向に動いた場合や、取引量を増やしすぎた場合 |
| 対策 | 常に委託保証金維持率を把握し、リスク管理を徹底すること。十分な保証金を預けておくことや、無理のない取引計画を立てること |
追証(おいしょう)と強制決済(ロスカット)
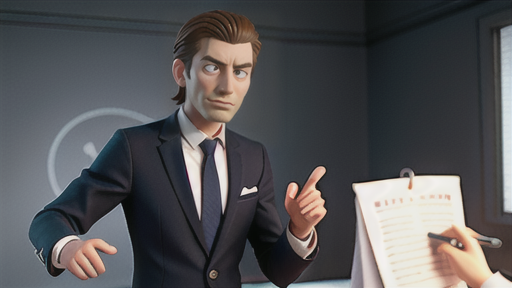
信用取引を行う上で追証と強制決済は避けて通れない重要な事柄です。追証とは、委託保証金維持率が一定水準を下回った際に、証券会社から追加の保証金を入金するよう求められることです。これは、損失が拡大し、預けている保証金だけでは損失を補填できなくなる可能性があるため、証券会社が投資家に追加の担保を求めるものです。もし追証が発生した場合、投資家は指定された期日までに不足金額を入金するか、保有している建玉の一部または全部を決済することで、委託保証金維持率を回復させる必要があります。しかし、期日までに追証を解消できない場合、証券会社は強制決済、いわゆるロスカットを行うことがあります。これは、証券会社が投資家の承諾を得ずに、強制的に建玉を決済することです。損失拡大を防ぎ、証券会社自身の損失を最小限に抑えるために行われます。強制決済が行われると、投資家は意図しないタイミングで損失が確定してしまいます。追証が発生しないように、委託保証金維持率を常に把握し、必要に応じて保証金を追加で預け入れるなどの対策を講じましょう。相場の変動リスクが高い時期には、建玉を減らすなどのリスク管理も有効です。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 追証(追加保証金) | 委託保証金維持率が一定水準を下回った際に、証券会社から追加の保証金を入金するよう求められること。 |
| 追証発生時の対応 | 指定期日までに不足金額を入金するか、建玉の一部または全部を決済して委託保証金維持率を回復させる。 |
| 強制決済(ロスカット) | 期日までに追証を解消できない場合、証券会社が投資家の承諾なしに強制的に建玉を決済すること。損失拡大を防ぐために行われる。 |
| 強制決済の影響 | 意図しないタイミングで損失が確定する。 |
| 対策 | 委託保証金維持率を常に把握し、必要に応じて保証金を追加で預け入れる。相場の変動リスクが高い時期には、建玉を減らすなどのリスク管理を行う。 |
委託保証金制度の注意点

信用取引を行う上で重要な委託保証金制度ですが、利用には注意が必要です。委託保証金は担保であり、利益を保証するものではありません。信用取引は大きな利益を得られる可能性がありますが、損失も拡大するリスクがあります。保証金額だけでなく、自身の投資目標やリスク許容度に合わせて慎重な取引を心がけましょう。
また、委託保証金維持率を常に把握し、追加保証金(追証)が発生しないように注意が必要です。維持率が低下すると追証が発生し、解消できない場合は強制決済される可能性があります。証券会社によって維持率の計算方法や追証の基準が異なるため、事前にルールを確認しましょう。
市場が大きく変動する時期には、維持率を高めに保つなど、リスク管理が重要です。株価が予想外の方向に動く可能性も考慮し、慎重な取引を心がけましょう。制度を理解し適切に管理することで、リスクを抑え安全な投資ができます。
| 項目 | 説明 | 注意点 |
|---|---|---|
| 委託保証金制度 | 担保として必要 | 利益を保証するものではない |
| 信用取引のリスク | 大きな利益の可能性 | 損失も拡大する可能性 |
| 委託保証金維持率 | 常に把握が必要 | 低下すると追加保証金(追証)が発生 |
| 追加保証金(追証) | 維持率低下で発生 | 解消できない場合は強制決済 |
| 証券会社のルール | 維持率の計算方法や追証の基準が異なる | 事前にルールを確認 |
| リスク管理 | 市場変動時に重要 | 維持率を高めに保つ |
| その他 | 投資目標やリスク許容度に合わせて慎重に取引 |
