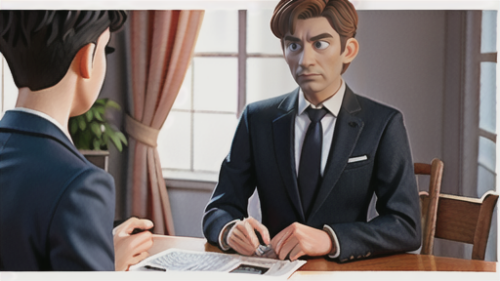法律
法律 紛争解決の糸口:あっせん制度とは
あっせん制度は、対立する二者の間に入り、問題解決を支援する仕組みです。当事者同士での話し合いが難しい場合に、第三者が仲介役となり、双方の意見を丁寧に聞き取ります。そして、それぞれの主張を理解した上で、互いの立場を尊重しながら合意点を探る手助けをします。この制度の目的は、裁判などの公式な手続きを避け、友好的な解決を目指すことです。あっせん人は中立的な立場でコミュニケーションを円滑にし、現実的な解決策を提案することで、紛争の早期解決を促します。裁判に比べて時間や費用を抑えられるだけでなく、当事者間の関係悪化を防ぐ効果も期待できます。感情的な対立や専門知識が必要な場合に、専門家が介入することで冷静な判断と建設的な議論を促し、解決への道筋を示します。この制度は、迅速かつ柔軟な紛争解決手段として、社会において重要な役割を果たしています。