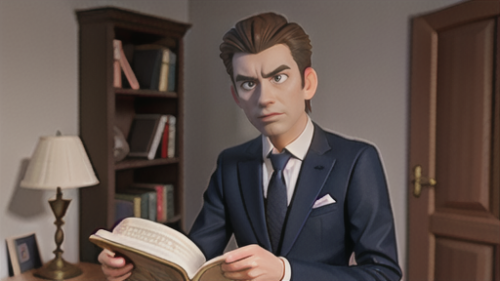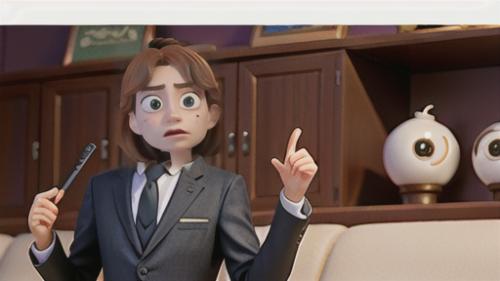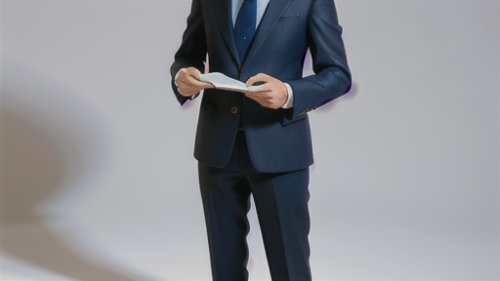その他
その他 国の財布を理解する:財政政策の基本
財政政策とは、国が経済の安定と発展のために行う、収入と支出に関する政策です。収入は主に税金であり、支出は公共事業や社会保障などが該当します。具体的には、国が道路や橋などの公共事業にお金を費やしたり、税金を減らしたりすることで、経済全体の動きを調整します。例えば、経済が停滞している時には、国が積極的に公共事業にお金を投入することで、新たな仕事が生まれ、企業の活動が活発になります。これにより、国民の所得が増え、消費も増え、経済が回復するという考え方です。逆に、経済が過熱している時には、国の支出を減らしたり、税金を増やしたりすることで、経済のスピードを緩めることが期待されます。このように、財政政策は経済の状況に応じて、様々な方法を使い分けて行われます。財政政策は、金融政策と並んで、国が経済を管理するための重要な手段の一つです。しかし、財政政策の効果が現れるまでには時間がかかることや、国の借金が増える可能性があることなど、注意すべき点も多くあります。財政政策を理解することは、私たちが暮らす社会の経済状況を把握し、将来を考える上で非常に大切な知識となります。