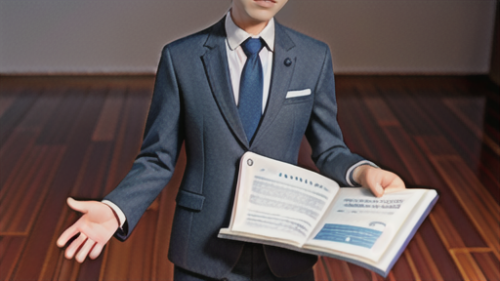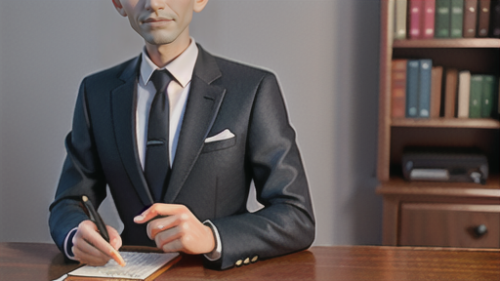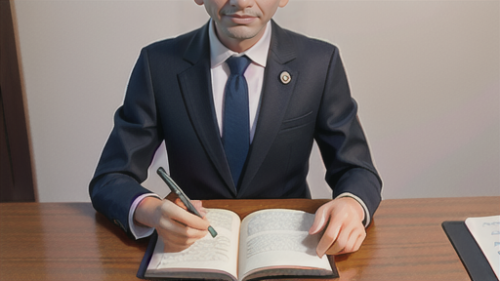 株式投資
株式投資 少額から始める株式投資:株式累積投資のすすめ
株式累積投資、通称「るいとう」は、まとまったお金がなくても毎月少しずつ株式を購入できる投資方法です。通常、株式はまとまった株数で購入する必要があり、それなりの資金が必要になりますが、株式累積投資では、毎月一定額、例えば1万円からといった少額で特定の企業の株式を積み立てていくことができます。これは、特に若い世代や投資を始めたばかりの方にとって、株式投資への心理的な壁を下げる魅力的な選択肢と言えるでしょう。毎月無理のない範囲で投資を続けることで、長期間にわたる資産形成を目指すことができます。また、価格変動リスクを軽減する効果も期待でき、株価が低い時には多くの株数を、高い時には少ない株数を購入することで、平均購入単価を抑えることが可能です。証券会社によっては、さまざまな会社の株式を取り扱っており、ご自身の興味や投資目標に合わせて投資先を選ぶことができます。株式累積投資は、少額から株式投資を始めたい方、長期的な視点で資産形成を考えている方にとって、非常に有効な手段となり得るでしょう。