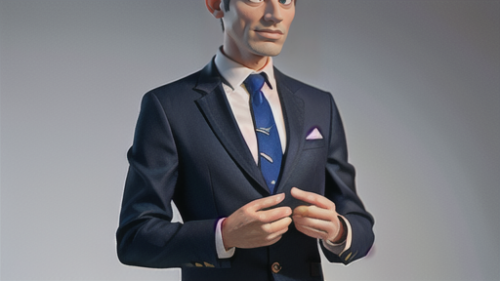株式投資
株式投資 投資における難平という手法:リスクと注意点
難平とは、投資において、保有する資産の価格が下がった際に、同じ資産を買い増し、平均取得価格を下げる手法です。例えば、ある株を1株1,000円で購入後、株価が800円に下落した場合、同じ株を800円で買い増すことで、平均購入価格を900円に下げられます。これにより、株価が再上昇した場合、最初に購入した時より早く利益を得られる可能性があります。しかし、価格が下落するほど買い増しを行うため、資金管理が重要です。計画なく難平を行うと、損失が拡大する可能性があります。難平を行う際は、価格がどこまで下落したら買い増しを行うか、どれだけの資金を投入するかを明確に決める必要があります。また、最初にその資産を購入した理由を再確認し、その理由が現在も有効かを検討しましょう。市場環境の変化や企業の業績悪化など、当初の投資判断を覆す状況が発生した場合は、損切りも検討しましょう。難平は投資戦略の一つであり、状況やリスク許容度を考慮し、慎重に判断することが大切です。