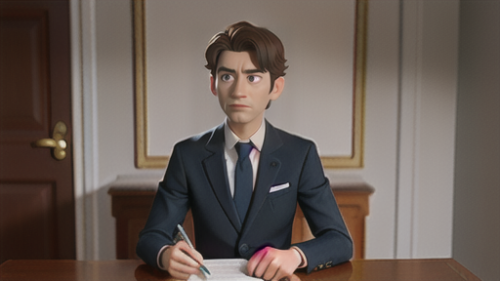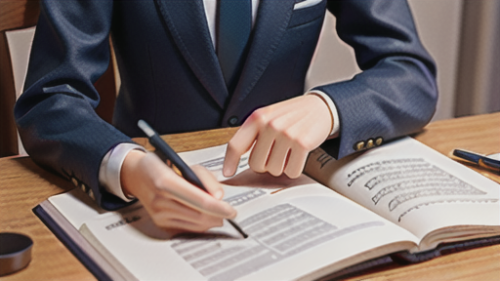投資信託
投資信託 市場の動きに連動する投資戦略:指標運用とは
指標運用とは、特定の市場の動きを示す指数、例えば、東証株価指数や債券指数といったものに連動した投資成果を目指す方法です。これは、市場全体の平均的な収益を得ることを目標とし、個別の企業を選んだり、将来の市場を予測することなく、市場全体の動きに沿って投資を行います。この運用方法は、積極的な運用とは異なり、市場は効率的であるという考えに基づいています。つまり、情報を集めたり分析に費用をかけても、常に市場の平均以上の成果を出すのは難しいと考えます。そのため、費用を抑えつつ市場全体の成長を取り込みたい投資家にとって、魅力的な選択肢となります。具体的には、指数に含まれる銘柄を、その割合に応じて投資することで、指数とほぼ同じ動きを目指します。この方法は、内容が分かりやすく、どのように運用されているか理解しやすいという利点があります。