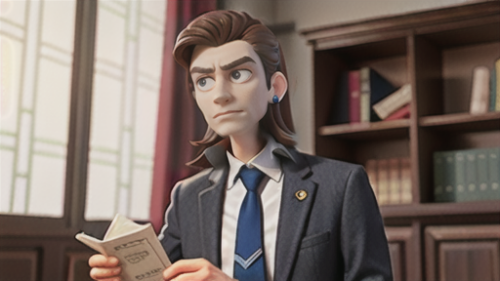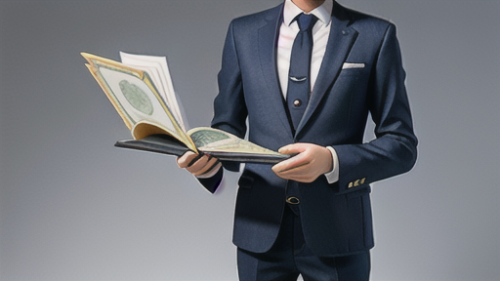投資情報
投資情報 海外からの安い商品流入が引き起こす物価下落
輸入物価の下落は、海外からの商品や役務が国内の価格水準に影響を与え、全体的な物価が下がる現象です。海外製品が低い製造費用で国内製品より安価になる場合や、円高により海外製品の円換算価格が下がる場合に発生しやすくなります。世界経済の繋がりが深まる中で、多くの国でこの現象が見られます。消費者にとっては、多様な商品を手頃な価格で入手できる利点がある一方、国内産業は価格競争の激化に直面し、経営が困難になる可能性があります。したがって、輸入物価の下落は経済全体に複雑な影響を及ぼすため、注意が必要です。