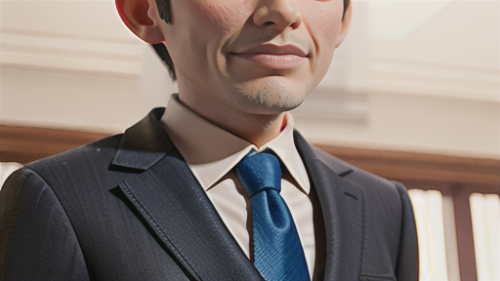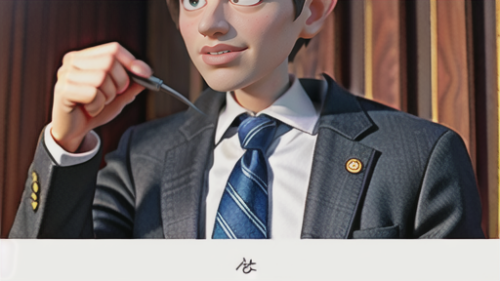投資情報
投資情報 小さく見て大きく知る:微視的分析で経済を理解する
微視的分析とは、経済全体を大まかに捉えるのではなく、個々の経済活動を行う主体、例えば、物を買う人や会社、特定の市場などに焦点を当てて詳しく調べる方法です。経済学でいうところの小規模経済学の考え方が基本となっており、物の値段が経済活動においてどのような役割を果たしているのかを細かく分析することで、経済全体の動きを理解しようとします。この分析方法は、別の名前として値段分析や小規模分析とも呼ばれます。個々の市場における需要と供給のバランス、会社の生産活動や物を買う人の行動など、経済を構成する最小単位の動きを詳しく観察することで、経済全体の複雑な動きを解き明かすことを目指します。例えば、ある商品の値段が変わることが、物を買う人の意欲にどのような影響を与えるのか、会社の生産量にどのような変化をもたらすのかといったことを具体的に分析します。また、特定の産業における競争状態や、政府の政策が個々の会社や物を買う人に与える影響なども分析対象となります。このように、微視的分析は、経済現象を細部にわたって理解するための強力な道具であり、政策を考えたり、会社の戦略を立てる上で欠かせない情報を提供します。