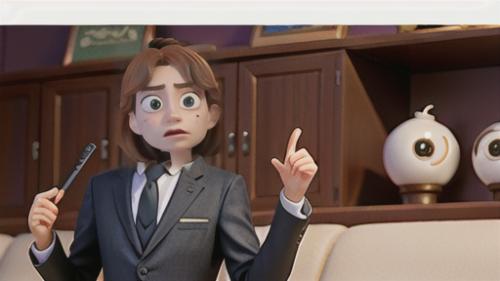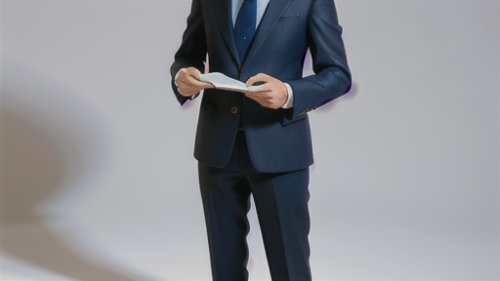外貨預金
外貨預金 海外通貨預金における支払い能力の安全性を測る指標
海外の通貨で貯蓄を行う際、金融機関が将来にわたり貯蓄者に資金を返せるだけの能力があるかは、非常に大切です。もし金融機関が経営破綻した場合、貯蓄保険制度が適用されないこともあり、貯蓄者の大切な資産が失われる危険性があります。支払い能力の安全性とは、このような危険から貯蓄者を守るための大切な指標です。この指標が高いほど、金融機関は不測の事態にも対応できる力があると言えます。貯蓄者は、海外の通貨で貯蓄を行う前に、必ず金融機関の支払い能力の安全性を確認し、信頼できる金融機関を選びましょう。金融機関の格付け情報や財務状況を参考に、様々な角度から金融機関の健全性を評価することも重要です。海外の通貨での貯蓄は、為替相場の変動による利益が期待できる一方で、金融機関の信用に関する危険も伴うことを理解しておく必要があります。危険を十分に理解した上で、慎重に判断し、安全な資産運用を心がけましょう。