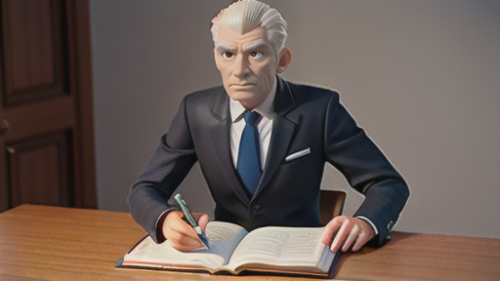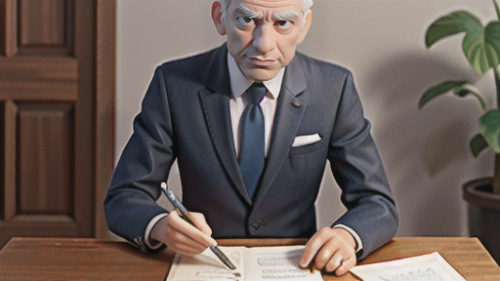税制
税制 国民識別番号の重要性と活用について
国民識別番号制度、通称番号制度は、社会保障、税、災害対策という、国民生活に欠かせない行政の働きを円滑にするために設けられました。各人に割り当てられる12桁の番号は、国内に住む全ての人、日本人も外国人も対象です。この制度のおかげで、行政機関は個人の情報をより正確に、素早く管理できるようになり、各種手続きが簡単になったり、サービスの質が向上することが期待されています。制度が始まった当初は、一人ひとりに番号通知書という形で番号が伝えられました。その後、顔写真付きの個人番号カードも発行され、身分証明書としても使えるようになり、さらに便利になりました。本格的な運用は平成28年から始まり、税の申告など、色々な行政手続きで番号の記載が必要となりました。しかし、使える範囲は限られており、会社年金への加入手続きなど、まだ使えない分野もあります。この制度をよく理解し、適切に利用することは、私たち一人ひとりが権利と義務をきちんと果たす上でとても大切です。