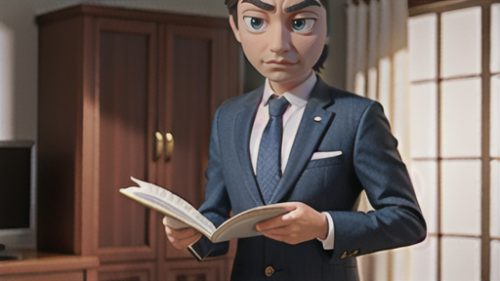年金
年金 設立事業所とは?わかりやすい解説
設立事業所とは、国の年金制度に加えて、企業独自の年金制度にも加入している事業所のことです。具体的には、厚生年金保険の適用を受けている事業所のうち、さらに厚生年金基金にも加入している事業所を指します。厚生年金保険の適用事業所とは、法律に基づき、従業員を厚生年金に加入させる義務がある事業所です。設立事業所は、この国の年金制度に加えて、企業が独自に運営する年金制度にも加入しているため、従業員の老後の生活をより一層手厚く保障することができます。企業は、設立事業所となることで、国の年金に上乗せして、独自の給付を従業員に提供することが可能です。これは、従業員の福祉向上に積極的に取り組む企業の姿勢を示すものと言えるでしょう。設立事業所であることは、企業が従業員の将来に対する責任を真剣に考えていることの表れであり、従業員にとって魅力的な職場環境を築く上で重要な要素となります。