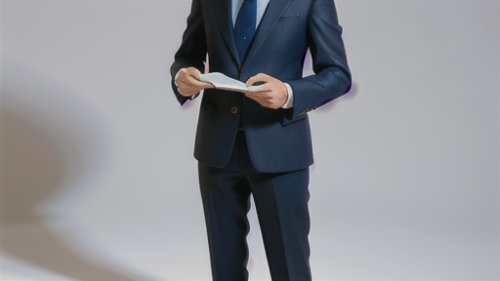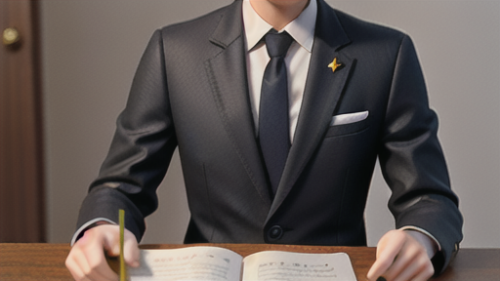個人向け社債
個人向け社債 異なる通貨でやり取りを行う債券とは?二重通貨建て外債の仕組み
二重通貨建て外債は、二種類の異なる通貨を組み合わせて取引される債券です。具体的には、債券を購入する際、利息を受け取る際、そして満期時に償還される際に、異なる通貨が用いられます。この仕組みにより、通常の債券とは異なる運用方法が可能になりますが、為替相場の変動リスクには注意が必要です。
例えば、日本円で米ドル建ての債券を購入し、利息も米ドルで受け取るとします。満期時には、再び日本円に換算して償還金を受け取ります。この時、為替相場の変動によって、最終的な収益が大きく左右される可能性があります。
二重通貨建て外債は、投資の選択肢を広げる手段の一つとなり得ますが、為替リスクを理解し、対策を講じることが重要です。投資を行う際には、ご自身の投資目標やリスクに対する許容度を考慮し、専門家と相談しながら慎重に検討することをお勧めします。