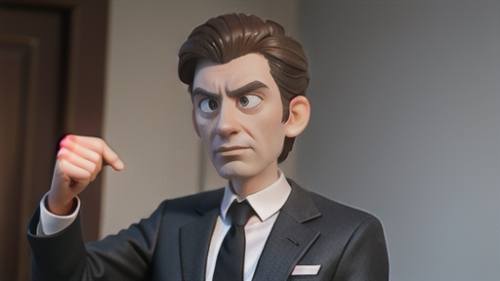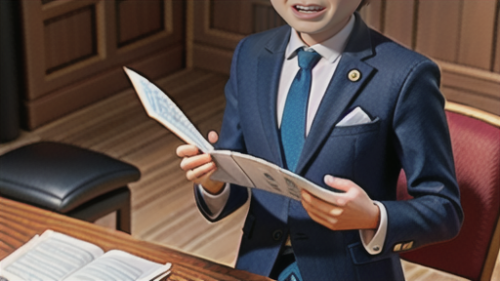投資情報
投資情報 関税貿易一般協定(ガット)とは? 経済の基礎を理解する
関税貿易に関する一般協定、通称ガットは、第二次世界大戦後の世界経済の安定を目指して生まれました。世界的な不況と大戦の反省から、各国が自国の経済を守るために貿易の壁を作ることが、国際的な緊張を高め、戦争の一因になったと考えられました。そこで、貿易の自由化を進め、世界経済の安定と発展を目指す国際的な枠組みとして、ガットが1947年に誕生しました。ガットの主な目的は、関税を下げることや、輸入制限などの貿易以外の障壁を取り除くことで、国際貿易を拡大することでした。これにより、各国は得意な分野に力を入れ、効率的な生産を行うことで、経済全体の成長を促すことができると考えられました。また、ガットは、最も恵まれた国と同じ条件をすべての加盟国に与えるという原則を掲げ、公平な競争環境を守ろうとしました。ガットは、その後、何度も多角的な貿易交渉を経て、その範囲を広げ、貿易の自由化をさらに進めました。これらの交渉では、関税を下げることだけでなく、知的財産権の保護や、サービスの貿易の自由化など、新しい分野も話し合われました。ガットは、半世紀近くにわたり、国際貿易のルールを定める上で重要な役割を果たし、世界経済の発展に大きく貢献しました。