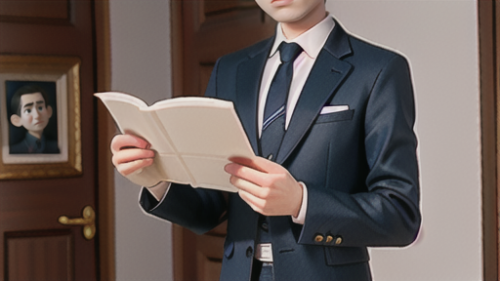FX
FX 国際取引を円滑にする通貨とは?基準通貨の重要性を解説
基準通貨とは、国際的な商取引や金融取引の決済に広く用いられる通貨を指します。別の呼び方として、国際通貨や基軸通貨とも呼ばれます。世界経済において非常に重要な役割を担っており、その国の経済力や政治の安定などが影響します。基準通貨としての地位を確立している通貨は、国際的な信用が高く、外国為替市場での流動性が高いため、取引が円滑に進みやすいという特徴があります。例えば、多くの国が輸出入の代金を米ドルで決済したり、外貨準備として米ドルを保有したりしています。そのため、米ドルの価値は世界経済に大きな影響を与えると言えるでしょう。基準通貨は、国際的な取引にかかる費用を削減し、為替変動による損失の危険性を軽減する効果も期待できます。異なる通貨を直接交換するよりも、いったん基準通貨に換算してから取引を行う方が、手数料や手間を省ける場合があります。また、為替相場の変動リスクを抑えることで、企業は安心して国際的な事業展開を進めることができます。しかし、基準通貨を持つ国は、その通貨の価値を安定させる責任を負うことになります。自国の経済政策が国際経済に大きな影響を与えるため、慎重な判断が求められます。