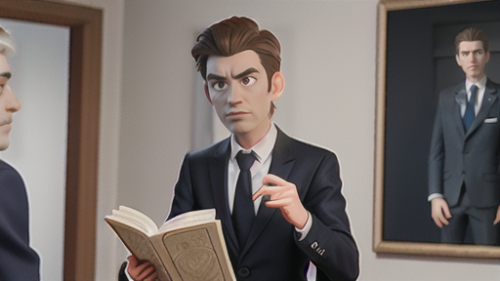 年金
年金 退職給付会計における数理計算上の差異とは?
退職給付会計における数理計算上の差異とは、将来の退職金や年金の支払義務を算出する際に用いる様々な見積もりと、実際の結果とのずれを指します。企業は、従業員の退職後に支払うべき金額を予測するために、金利水準、賃金の上昇率、従業員の退職率や死亡率など、多くの仮定を置いて計算します。しかし、これらの仮定は未来の出来事を予測するものであるため、どうしても実際の状況との間に差が生じます。例えば、運用利回りが当初の見込みを下回った場合、退職給付債務は増加し、これが数理計算上の差異として現れます。このような差異は、企業の財務状況に影響を与えるため、会計基準に沿った適切な処理が求められます。企業は、数理計算上の差異を注記などで開示することで、財務諸表の利用者に将来の不確実性に関する情報を提供し、より適切な経営判断を支援することが重要です。

