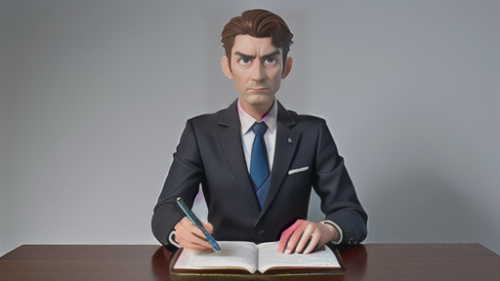年金
年金 確定拠出年金における運用指図者の役割と重要性
確定拠出年金において、運用指図者とは、掛金を拠出せずに、既に積み立てられた資金の運用指示のみを行う方を指します。例えば、退職や転職で企業型年金の加入資格を失った場合や、個人型年金(iDeCo)加入者が運用のみを行う期間が該当します。掛金の拠出がないため、資産を増やすことはできませんが、積み立てた資産をどう運用するかを決める重要な役割を担います。運用指図者は、年齢、リスク許容度、投資目標を考慮し、預金や投資信託などから最適な組み合わせを選択します。市場動向を注視し、必要に応じて見直しを行うことも重要です。将来の年金額を左右するため、慎重かつ計画的な運用が求められます。金融機関の情報やセミナーを活用し、金融知識を高めることも大切です。運用指図者は、自らの老後生活を担う責任ある役割と言えるでしょう。