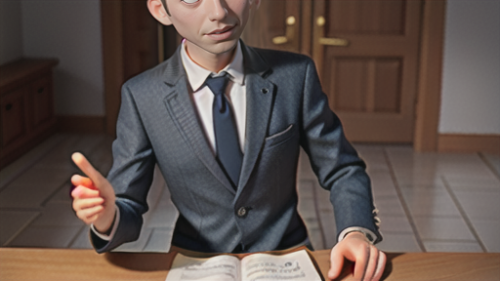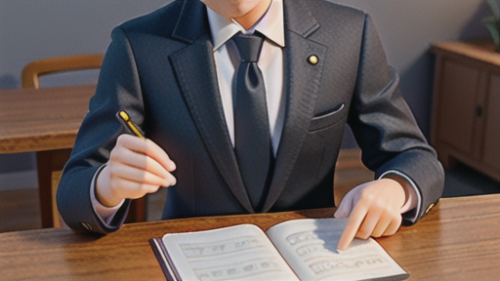株式投資
株式投資 株価下落の兆候? 危険な兆候「下降交差」とは
株式投資の世界では、過去の株価動向を基にしたテクニカル分析が広く用いられます。その中で「下降交差」は、相場の転換点を示唆する重要な指標の一つです。これは、株価の動きを示す移動平均線を利用します。移動平均線には短期、中期、長期があり、短期の線が長期の線を下回る状態が下降交差です。一般的に、この現象は株価が下落する可能性を示唆し、売り時を判断する手がかりとされます。しかし、下降交差が発生したからといって、必ず株価が下落するわけではありません。他のテクニカル指標や市場全体の状況と合わせて総合的に判断することが大切です。また、過去のデータに基づく分析であることを理解し、投資判断は自己責任で行う必要があります。リスク管理を徹底し、慎重な投資判断を心がけましょう。