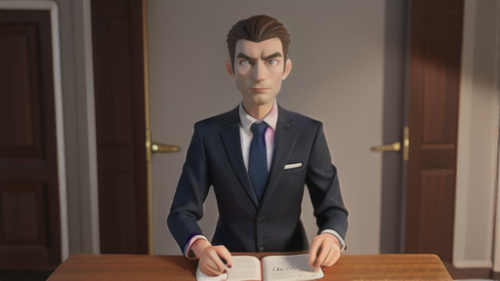投資情報
投資情報 建築需要が左右する景気変動:クズネッツ循環とは
クズネッツ循環とは、約二十年の周期で繰り返される経済の変動を指し、主に建築物の需要変動が原因と考えられています。これは、米国の経済学者であるシモン・スミス・クズネッツによって提唱されました。彼は国民所得の概念を確立し、経済成長の測定方法を開発したことで知られています。この循環は彼の名から「クズネッツの波」や「建築循環」とも呼ばれます。長期的な経済動向を予測し、適切な投資戦略を立てる上で、この循環を理解することは非常に重要です。建築需要は、住宅、事務所、公共施設など、経済活動の基盤となる様々な要素を含みます。そのため、建築需要の変動は経済全体に大きな影響を与えます。例えば、建築需要が増加すると、建設業界だけでなく、鉄鋼やセメントなどの関連産業も活性化し、雇用の創出にも繋がります。反対に、建築需要が減少すると、これらの産業は不況に陥り、失業率の上昇を招く可能性があります。したがって、クズネッツ循環を把握することは、経済政策の策定や企業経営においても不可欠な要素と言えるでしょう。