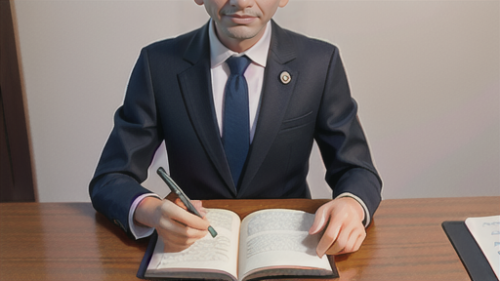NISA
NISA 少額投資非課税制度を活用して賢く資産形成
少額投資非課税制度、通称NISAは、個人の資産形成を後押しする国の税制優遇策です。通常、投資で得た利益には税金がかかりますが、NISAを利用すれば、一定額までの利益が非課税になります。例えば、株式や投資信託などの金融商品から得られる配当金や、売却益が対象です。投資に関心があっても税金が心配だった方にとって、NISAは魅力的でしょう。投資初心者でも始めやすく、少額から着実に資産を増やせる可能性があります。将来の資金準備や老後の生活資金など、様々な目的に活用できます。制度を理解し、ご自身の人生設計に合わせて賢く利用しましょう。金融機関の窓口やウェブサイトで詳細を確認できます。