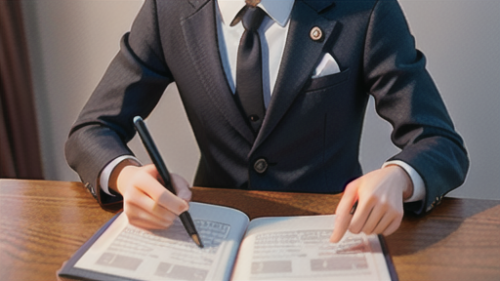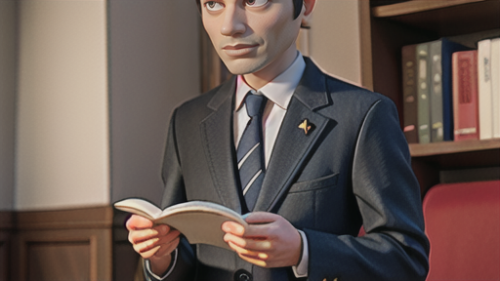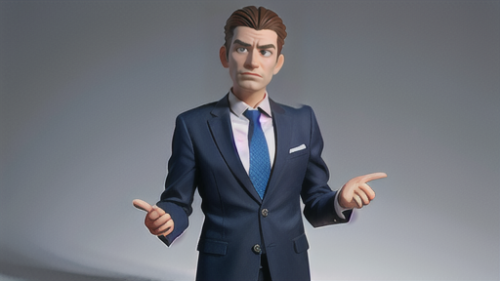投資信託
投資信託 投資判断の羅針盤:目論見書を徹底解剖
目論見書は、株式や債券といった有価証券への投資を検討する上で、非常に重要な情報源となる書類です。これは、有価証券を発行する企業や政府などが、投資家に対してその内容を詳しく説明するために作成し、提供するものです。投資家が「この有価証券はどのようなものなのか」「投資する価値があるのか」を判断するための、いわば取扱説明書のような役割を果たします。目論見書には、発行体の事業内容や財務状況、投資に伴う危険性、有価証券の詳しい条件(利率や償還期間など)、資金の使い道などが詳細に記載されています。これらの情報を十分に理解することで、投資家は危険性と期待される収益を総合的に判断し、自身にとって最適な投資判断を下すことができます。金融商品を購入する際には、必ず目論見書を読み込み、内容を十分に理解することが、賢明な投資を行うための第一歩です。今日では、インターネットを通じて電子的に提供される目論見書を、パソコンやスマートフォンで容易に閲覧できます。時間や場所を選ばずに情報収集できるため、目論見書を積極的に活用した投資判断がますます重要になっています。