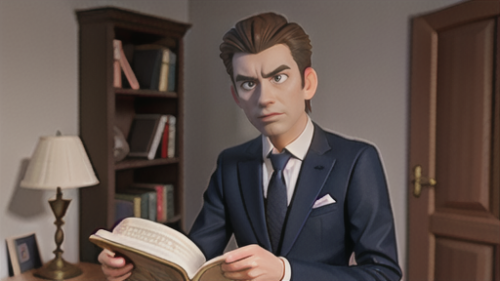投資情報
投資情報 価格が動かない?経済を読み解く価格の硬直性
価格の硬直性とは、市場で取引される物の値段が、需給の変化にすぐさま対応せず、しばらくの間、同じ水準を保つ状態を指します。本来、市場経済では、需要が増えれば値段は上がり、供給が増えれば値段が下がるのが基本です。しかし、現実には、企業が値段を変えるのに費用がかかったり、顧客との関係を大切にして値段を安定させたりするなど、様々な理由で値段がすぐに変わらないことがあります。このような価格の硬直性は、経済全体に大きな影響を与える可能性があります。もし需要が減っているのに値段が下がらないと、商品が売れ残り、在庫が増えてしまいます。逆に、需要が増えているのに値段が上がらないと、品薄になり、消費者は物を手に入れにくくなります。価格の硬直性は、市場の調整機能を妨げ、経済の効率を悪くする要因となるため、経済政策を考える上で重要な要素となります。