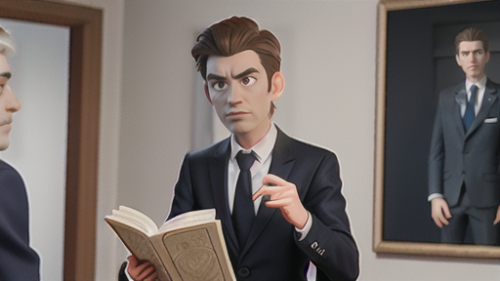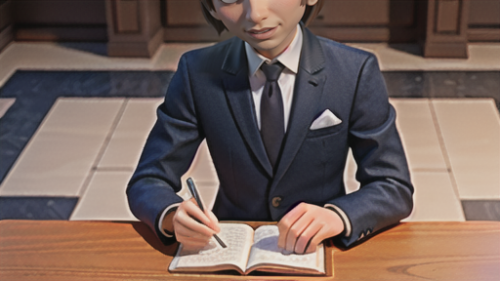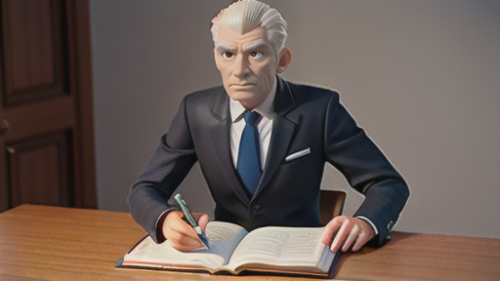年金
年金 退職給付会計における勤務費用の重要性
勤務費用とは、企業が従業員の退職後に支払う退職給付のうち、従業員が当期に労働を提供したことによって新たに発生したと見込まれる給付の現在価値を指します。これは、従業員が一年間会社のために働いたことへの対価として、将来支払われる退職給付のうち、当期に相当する部分を現在の価値に換算したものです。この勤務費用は、企業の将来的な退職給付債務を評価する上で重要な指標となります。投資家や債権者などの利害関係者は、企業の財務状況を分析する際に、この勤務費用を含む退職給付費用全体を注視し、企業の将来の支払い能力を判断します。勤務費用の計算は、複雑な数理計算に基づいています。従業員の給与、勤続年数、退職率、割引率などの要素を考慮し、将来の給付額を予測し、それを現在価値に割り引くことで算出されます。そのため、企業は専門家である年金数理人の助けを借りて、正確な勤務費用を算定する必要があります。