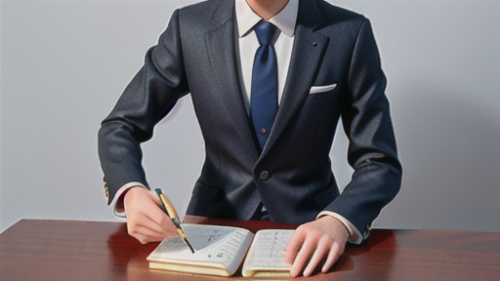金投資
金投資 金投資と通貨供給量の関係性:マネタリーベースとは
金への投資を検討する際、経済全体の資金の流れを把握することは不可欠です。その流れを理解する上で重要な指標となるのが、資金供給量(マネタリーベース)です。これは、中央銀行が金融機関へ供給する通貨の総量を指します。日本においては、日本銀行が発行する日本銀行券の発行高、市場に流通する貨幣の流通高、そして金融機関が日本銀行に預けている当座預金の合計額で計算されます。つまり、資金供給量(マネタリーベース)は、経済活動の基盤となる通貨がどれだけ供給されているかを示す、通貨供給の源となる数値です。この数値を理解することで、金投資を含む多様な投資判断において、より深い分析が可能となります。