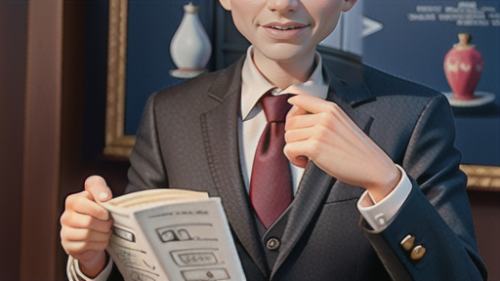国債
国債 米国財務省証券「トレジャリー」とは?その種類と市場への影響
トレジャリーとは、米国の財務省が発行する債券のことで、日本における国債に相当します。米国政府が資金調達のために発行し、その信用度の高さから世界中の投資家にとって重要な投資先となっています。トレジャリーは、満期までの期間によって大きく3種類に分類されます。満期が1年以内のものはトレジャリー billと呼ばれ、2年から10年以内のものはトレジャリー note、10年を超えるものはトレジャリー bondと呼ばれます。これらの債券はそれぞれ特徴が異なり、投資家の需要やリスク許容度に応じて選択されます。例えば、トレジャリー billは比較的短期での運用を考えている投資家にとって魅力的です。一方、トレジャリー bondは長期的な安定収入を求める投資家に適しています。米国国債は世界で最も流通量が多く、活発に取引されている債券の一つであり、その価格や利回りの変動は世界の金融市場全体に大きな影響を与えます。特に、長期金利の指標となる10年物国債の利回りは、住宅ローン金利や企業の借入金利など、様々な金利に影響を及ぼし、経済全体の動向を左右する重要な要素となります。