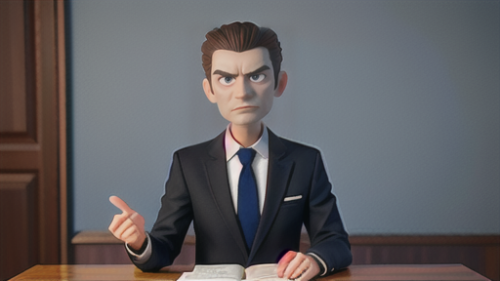外貨預金
外貨預金 為替相場安定化策:外貨預金と通貨発行制限
為替相場の変動は、私たちの暮らしや経済に大きな影響を与えます。輸入品の価格上昇や企業の収益悪化、海外旅行費用の増加など、影響は多岐にわたります。そのため、各国はさまざまな方法で為替相場の安定化を図っています。その手段の一つとして、外貨預金が注目されています。外貨預金とは、日本円ではなく、外国の通貨で預金を行うことです。個人の資産運用として利用されることが多いですが、国によっては為替相場の安定化に役立てることを目的として、外貨預金を推奨したり、制度を設けたりしています。特に、自国の通貨の価値が不安定な国や、海外との貿易への依存度が高い国では、外貨預金を通じた為替相場安定化策が重要な意味を持ちます。外国の通貨準備を増やし、通貨の信頼性を高めることで、経済全体の安定につなげようとする試みです。