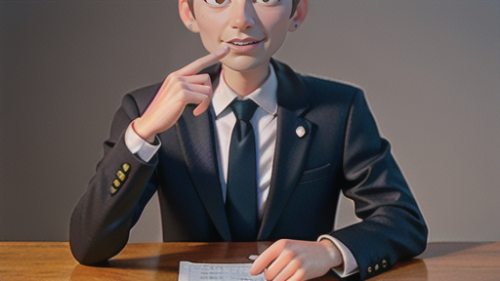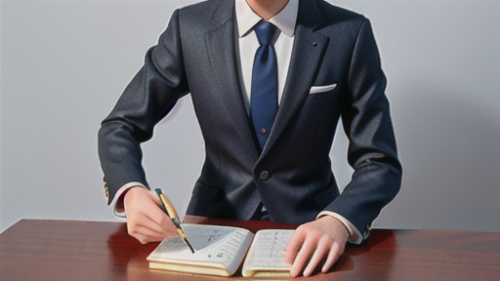株式投資
株式投資 株式投資における端株とは?過去の制度から学ぶ投資戦略
株式投資において端株とは、一株に満たない株式を指します。過去には、株式分割や株式割当などで生じることがありました。例えば、一株を1.5株に分割する場合、元々一株持っていた投資家は1.5株となります。この0.5株が端株です。株主優待で株式が追加される際にも発生しました。端株は少額投資を可能にする一方、売買単位が一株以上なので、そのままでは市場で取引できませんでした。そのため、会社による買取や、他の投資家からの買い増しが必要でした。現在、株券電子化により端株制度は廃止されましたが、過去の制度を知ることは、今の投資戦略にも役立ちます。