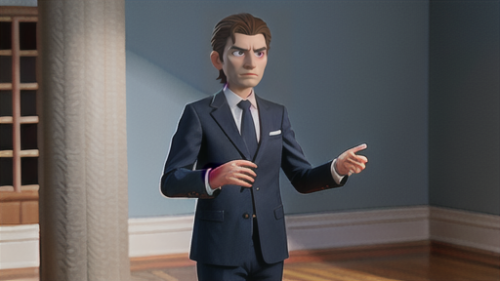投資情報
投資情報 運用成果を測る物差し:指標比較とは
指標比較は、投資信託や年金といった資金運用の成果を測る上で欠かせない手法です。これは、運用によって得られた収益率を、市場全体の平均的な収益率を示す基準となる指標(参照指数)と照らし合わせることで、その運用が市場平均と比べてどれほど優れているか、あるいは劣っているかを評価するものです。この比較を行うことで、運用者の能力や、採用されている運用戦略の効果を客観的に判断することができます。適切な指標を選ぶことが重要で、例えば、国内の株に投資するものであれば、東証株価指数や日経平均株価が用いられます。海外の株に投資するものであれば、世界の株価を示す指数が適切でしょう。指標比較では、単に収益率の高さを比べるだけでなく、リスクを考慮した収益率や、どれだけ継続して市場平均を上回る収益を上げているかなども考慮に入れる必要があります。これにより、より深く運用成果を分析し、改善につなげることが可能になります。