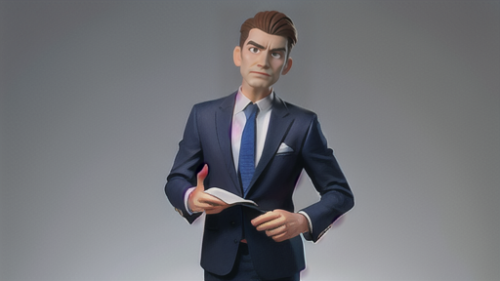投資情報
投資情報 資産の価値変動を理解する:評価損益とは
資産を運用する上で、評価損益は非常に大切な考え方です。これは、私たちが持っている資産の価値が変わることで生じる、まだ実現していない利益や損失のことです。例えば、今持っている株や不動産などを売ったらいくらになるかを計算し、その結果が元の値段より高ければ評価益、低ければ評価損となります。これは実際に売買したわけではないので、「含み益」や「含み損」として扱われます。評価損益を理解することで、自分の資産全体のリスクを知り、より良い投資判断ができます。もし評価益が大きければ、利益を確定するために一部を売ることも考えられますし、評価損が大きければ、損失がさらに大きくならないように売ってしまうことも考える必要があります。このように、評価損益は、投資の計画を立てる上で欠かせない情報となります。さらに、評価損益は、税金の計算にも関係してきます。実際に利益が出た場合は税金がかかりますが、まだ実現していない評価益には通常は税金はかかりません。しかし、場合によっては評価益にも税金がかかることがあるので注意が必要です。評価損益を正しく理解し、適切に管理することが、資産を増やしていく上で非常に重要です。