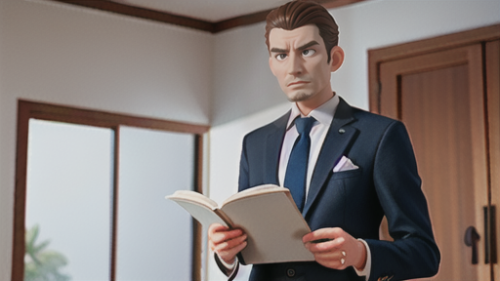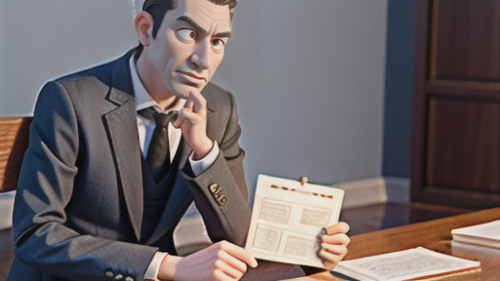投資情報
投資情報 幻に終わった国際貿易機構:自由貿易への道のり
国際貿易機構、通称ITOは、第二次世界大戦後の世界経済の立て直しと、より自由で公平な貿易の仕組みを作るために、アメリカ合衆国が中心となって提案された国際機関です。世界恐慌時代の保護主義的な貿易政策への反省から、貿易の妨げとなる壁を取り除くことによって、世界経済の安定と成長を目指しました。具体的には、関税の引き下げ、輸入制限の緩和、差別的な貿易慣行の禁止などを内容とする協定を結び、それらを監督する役割を担うはずでした。しかし、理想とは異なり、ITOは様々な政治的、経済的な理由から実現しませんでした。設立までの過程や、頓挫した理由を知ることは、現代の国際貿易の仕組みを理解する上で重要です。国際貿易機構が目指した公平で自由な貿易という考え方は、後の世界貿易機関(WTO)に引き継がれ、国際社会の経済発展に貢献しています。