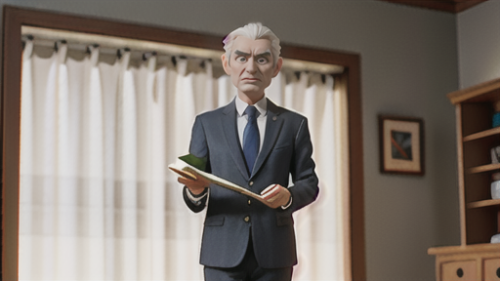その他
その他 仕組み債券の一種、合成債務担保証券とは?
合成債務担保証券は、現物の債券を直接使わずに、信用リスクを移転させる金融商品です。具体的には、クレジット・デフォルト・スワップという契約と、国債や社債などの担保となる債券を組み合わせて作られます。従来の債務担保証券は、実際に存在する債権を裏付けとしていましたが、合成債務担保証券は、この点が大きく異なります。組成者は、現物の債権を購入することなく、様々な債権の集まりが持つリスクを取引できます。しかし、その構造は複雑で、リスクを正確に把握することが難しいという側面があります。市場の変動によって大きく影響を受ける可能性があり、金融危機時には、そのリスクが表面化し、市場全体に悪影響を及ぼした事例もあります。投資を行う際には、高度な金融知識とリスク管理能力が求められるため、注意が必要です。