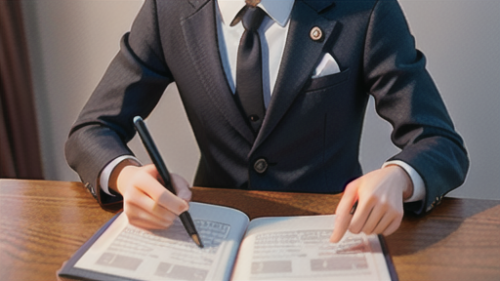NISA
NISA 非課税投資枠の活用術:ロールオーバーを徹底解説
非課税期間が満了した少額投資非課税制度(NISA)口座で保有する金融資産を、翌年の非課税投資枠へ移管することを「繰越」といいます。この制度は、投資によって得た利益に税金がかからないという利点がありますが、非課税で投資できる期間には上限があります。そのため、期間終了後も引き続き運用したい場合に、繰越という仕組みを利用できます。通常、投資で得た利益には税金が発生しますが、この制度を利用することで税金が免除され、より効率的な資産形成につながります。制度を適切に利用することで、非課税の恩恵を最大限に受け、長期的な資産形成を有利に進めることが可能です。非課税期間が終了する際、金融資産の売却を検討する方もいますが、繰越を利用すれば、売却せずに非課税のまま運用を継続できます。ただし、繰越を行うにあたっては、いくつかの注意点があります。例えば、翌年の非課税投資枠を上限まで使ってしまう可能性があることや、繰越の手続きが必須であることなどが挙げられます。これらの注意点を考慮した上で、繰越を活用することで、賢く資産を増やしていくことができるでしょう。