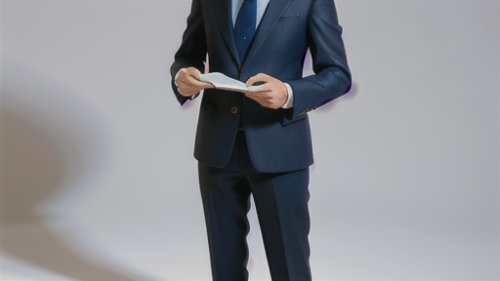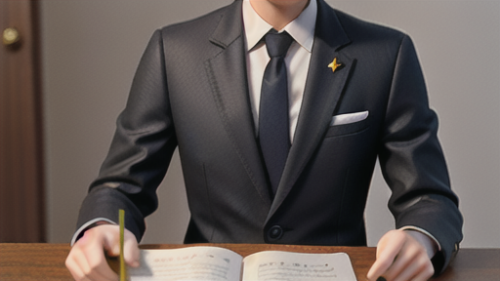国債
国債 現先取引とは?仕組みと活用方法をやさしく解説
現先取引は、債券などの有価証券を、将来の特定日に予め定めた価格で買い戻す、または売り戻す約定のもとで売買を行う取引です。主に、一時的な資金の調達や運用手段として、金融機関などで広く活用されています。例えば、甲社が乙社に債券を売却し、同時に数日後、あるいは数週間後にその債券を買い戻す契約を結ぶ場合、甲社は一時的に資金を得られます。乙社は、その期間、債券を担保として保有し、買い戻し価格との差額が実質的な利息となります。現先取引は、短期的な資金の貸し借りを行う上で有効な手段であり、金融市場における資金の流れを円滑にする役割を担っています。通常の債券売買とは異なり、最初から将来の買い戻し、または売り戻しが約束されている点が特徴です。この約束により、取引を行う当事者は将来の資金の流れを予測しやすくなり、危険を管理しやすくなるという利点があります。また、中央銀行が金融政策を実行する際にも用いられることがあります。中央銀行が金融機関から債券を買い入れ、将来買い戻すという形で資金を供給することで、市場の金利を調整したり、資金の流れを調整したりすることが可能です。このように、現先取引は、金融市場において多様な役割を果たしており、その仕組みを理解することは、金融市場を深く理解する上で重要となります。