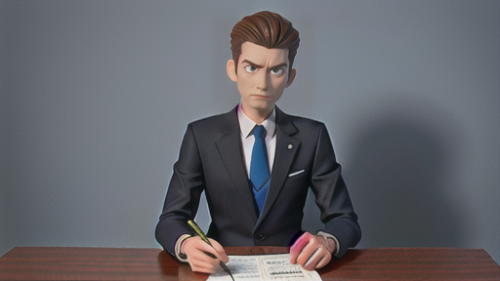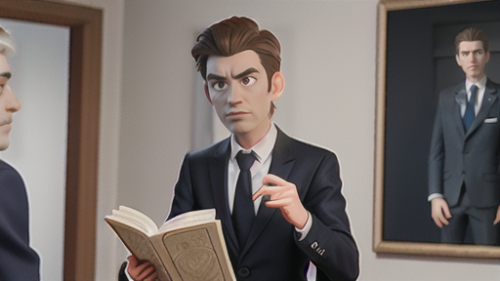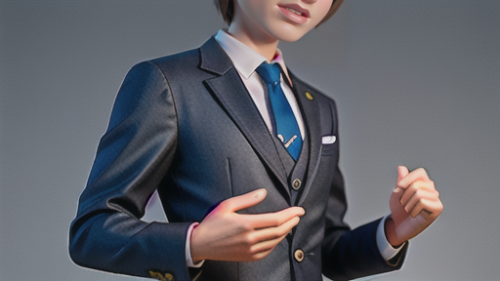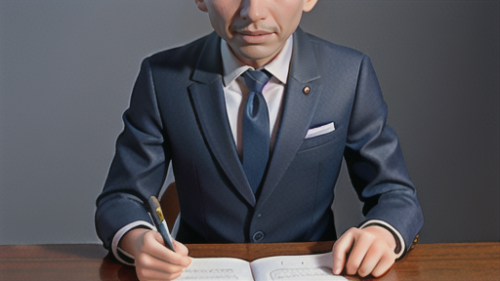年金
年金 積立期間中の利率固定:据置利率とは?
積立型の金融商品における据置利率とは、積立期間満了後、給付開始までの期間に適用される利息の割合を指します。この期間、積立金は運用され、その運用益が将来の受取額を左右します。特に、老後資金準備など長期の積立商品では、据置利率の確認が重要です。据置期間中は、資金を引き出さずに据え置くことで、より高い利息を得ることを目指します。据置利率は、金融機関や商品によって異なり、市場の金利動向や各金融機関の経営状況によって変動する可能性があります。商品を選ぶ際は、据置利率だけでなく、据置期間や解約時の手数料も考慮し、総合的に判断することが大切です。固定の据置利率であっても、物価上昇により実質的な価値が減少するリスクも考慮に入れる必要があります。将来設計に合わせて最適な商品を選び、計画的な資産形成を行いましょう。