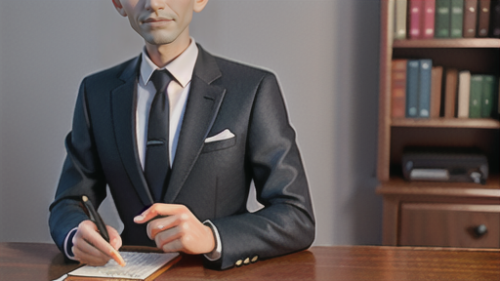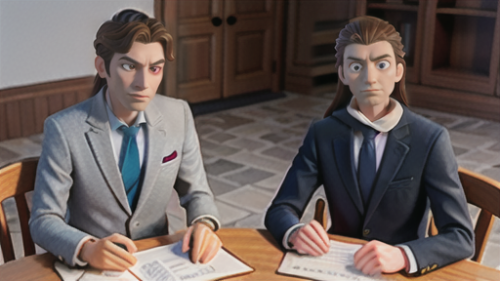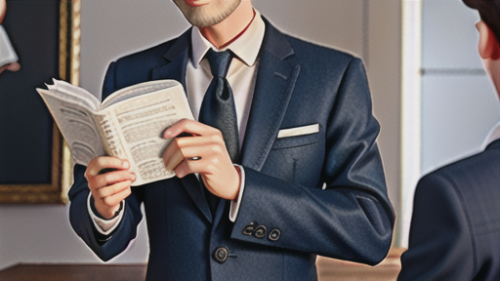その他
その他 荷為替手形の基礎知識と活用法
荷為替手形は、国際的な取引、特に輸出入において用いられる決済方法の一つです。輸出を行う者が、輸入を行う者に対して振り出す手形に、商品の引換券となる船荷証券などの書類を添付したものを指します。この仕組みにより、輸入者は代金を支払うことで、商品を受け取るための書類を確実に手に入れることができます。一方、輸出者にとっては、代金が確実に回収できるという安心感があります。これは、両者にとってリスクを減らすことができる合理的な方法と言えるでしょう。信用状取引と並び、国際貿易で広く利用されており、特に輸出者と輸入者の間に十分な信頼関係がない場合や、取引金額が大きい場合に有効です。銀行が仲介役となることで、取引に伴う様々なリスクを軽減し、円滑な貿易を支援します。荷為替手形を利用することで、国際取引における不確実性を減らし、より安全で効率的な貿易取引を実現することが可能になります。